

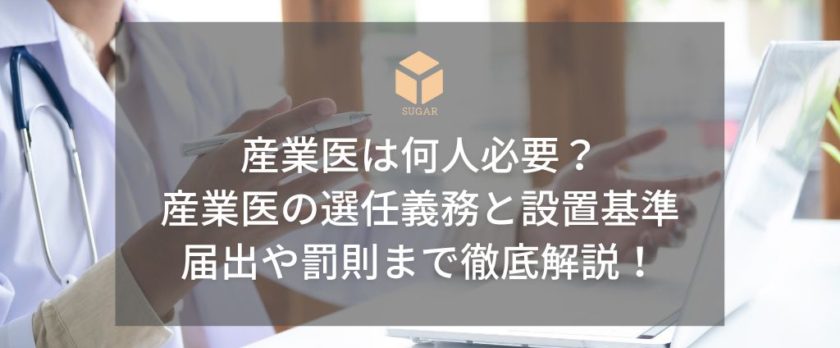
産業医の選任は、労働安全衛生法によって事業者の義務であると定められています。ただし、従業員数によって選任義務がない場合があったり、業種によって必要な産業医の数が異なったりと、選任義務の規定は複雑です。
「自社に産業医が何人必要なのかわからない…」
「常勤雇用ではなく、月1回の業務委託でもいいのか?」
「いつまでに選任すればいいのか?」
などと、産業医選任についてわからず、お悩みの企業担当者も多いのではないでしょうか。今回は、複雑な産業医選任義務について、設置人数と注意すべきルールを解説します。法令を正しく理解し、万全な安全管理体制を整えましょう。

労働安全衛生法において、常時50人以上の従業員を雇用している事業場では、産業医を選任する義務があると定められています。しかし、産業医が何人必要かは事業場の規模によって異なり、設置基準や条件は複雑です。
正しく理解するためには、「50人」「1,000人以上」という2つの基準をおさえておくとよいでしょう。
選任が求められる産業医の人数は、常時雇用している従業員の人数により変わります。以下のように、従業員が50人以上かどうかが1つの基準といえるでしょう。
専属産業医とは、企業に雇用され、定められた勤務時間帯に準じて勤務する産業医を指します。一方で、月1回などのペースで企業に出向く嘱託契約の場合には、嘱託産業医です。
労働安全衛生規則において、1,000人以上の従業員を雇用している事業場では、専属産業医の選任が必要と定められています。1,000人未満であれば、嘱託産業医の選任が可能です。
ただし、有害物質などを扱う業種では、500人以上で専属産業医を選任する義務があるため、注意が必要です。以上の点をまとめると、次の4つの人数基準をおさえておくとよいでしょう。
参考:厚生労働省 産業医の関係法令「労働安全衛生規則 第13条第1項」
専任産業医とは、産業医が産業医としての業務のみに従事することを指します。労働安全衛生規則において、従業員1,000人以上の事業場に定められているのは、「専属」産業医の選任です。
企業に所属する専属産業医であれば、法令上は問題ありません。たとえば、専属産業医が企業内クリニックで診療を行ったとしても、違反に問われることはないのです。ただし、産業医の業務に支障をきたさない程度にとどめる必要はあるでしょう。
「専任」と「専属」は混同しやすいため、両者の違いを把握し、産業医の設置義務を正しく理解しましょう。

定められたルールにもとづいて産業医の選任や届出を行わない場合、罰金が課せられるケースがあります。産業医選任のルールを正しく理解することが大切です。
産業医は、従業員の心身の健康を守るべく、産業医学の知見をベースに実践を行います。臨床医とは異なる専門性が必要であるため、産業医としての研修や試験を修了・合格していることが認定条件です。以下のような要件があるため、選任にあたって確認するとよいでしょう。
参考:厚生労働省 産業医の関係法令「労働安全衛生規則第14条第2項」
産業医の選任は、選任が必要となった時点より14日以内に決定し、管轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
選任が必要となる時点とは、従業員の数が増え、新たに産業医を選任しなければならないときです。たとえば、従業員数が48人だった事業場に、新規採用で2人の増員があった場合は新たに産業医を選任する必要があります。
また、「来年度から従業員数が3,000人以上になってしまう」など、すでに産業医がいても新たに選任義務が生じる場合もあるでしょう。14日以内に届け出られるよう、さまざまなケースを想定しておかなければなりません。
参考:厚生労働省 産業医の関係法令「労働安全衛生規則第13条第1項」
産業医選任の義務があるにもかかわらず、14日以内に届出をしなかった場合、50万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
14日以内の選任期間に間に合うように、従業員の増減状況について把握し、計画的な産業医選任を行う必要があるでしょう。

産業医の選任においては、設置基準や選任、届出の期限を遵守する必要があります。
とくに、「何人の産業医が必要なのか」「雇用形態は嘱託か専属か」など、従業員数や業種により選任義務は変わります。今回ご紹介したポイントから自社の選任義務を整理するとよいでしょう。
産業医は、法令遵守のためだけに選任されるものではありません。従業員の健康を守り、組織としてのパフォーマンス向上の一翼を担うものだといえます。万全な安全管理体制を整え、健康経営を意識した組織づくりを推進していきましょう。