

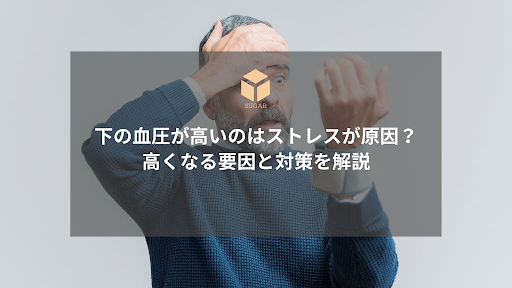
血圧には、上の血圧(収縮期血圧)と下の血圧(拡張期血圧)があります。「上の血圧は正常だけど、下の血圧だけ高い」「下の血圧だけ高いので気をつけるように言われた」といった経験はありませんか。
どちらかの血圧が高い状態でも、高血圧と診断される場合があり、下の血圧だけが高くても健康上のリスクがあります。また、下の血圧の上昇には、仕事上のストレスが関係している場合も多く、健康管理を行う上で注意が必要です。
本記事では、下の血圧が高いと指摘された人に向けて、健康上のリスクとストレスの関連性について解説します。血圧上昇を見逃さず、適切な対処方法を理解しましょう。
上の血圧(収縮期血圧)は高くないのに、下の血圧(拡張期血圧)だけが高くなるのは、どのような原因が考えられるのでしょうか。原因としては、手足の血流や年齢が関係しているとされています。
血圧は、心臓から血液を送り出しているときと、心臓に血液が流れ込むときを計測します。前者が収縮期血圧で、後者が拡張期血圧です。送り出した血液が血管に流れ込み圧力がかかるため、収縮期血圧は高くなります。
一方で、血液が心臓に流れ込んでいくと血管の血液量は低下し、圧力が弱まるため、拡張期血圧は低いです。そのため、拡張期血圧が高い状態は、「心臓に血液が流れ込んでいるのに、血管の圧力があまり弱まっていない」状態といえます。
原因の一つとしては、手足に張りめぐらされた末梢血管が硬くなっているためだと考えられます。心臓に血液が流れづらくなり、心臓にうまく血液が戻っていかないためです。また、血液がドロドロの状態でも生じる可能性があり、あまり良い状態とはいえないでしょう。
加齢に伴って血管が硬くなるため、収縮期血圧は高くなり、拡張期血圧は低くなりやすいとされています。そのため、高齢者は拡張期血圧が高くなりにくい傾向があるでしょう。
また、若いころは、生活習慣が乱れていても、心臓に近い血管は影響を受けず、収縮期血圧が高くならないことがあります。
そのため、収縮期血圧はあまり高くならずに、拡張期血圧だけが高くなるという現象が起きやすいです。
拡張期血圧が高いと、拡張型心筋症に近い状態になる可能性があります。拡張型心筋症とは、心臓の筋肉が弱り、血液を全身に送り出す力が低下する病気であり、慢性心不全の原因にもなります。
拡張型心筋症は、初期には倦怠(けんたい)感や疲労感、息苦しさが主な症状で見過ごされてしまうこともあります。収縮期血圧に注目しがちですが、拡張期血圧にも注意して、適切な治療を受ける必要があるでしょう。
ストレスにより高血圧の発症が約2倍以上高まるとされており、ストレスは高血圧と密接に関係しています。そのため、ストレスによる血圧上昇により、拡張期血圧も高くなりやすいといえるでしょう。なぜ、ストレスがかかると血圧が上昇するのでしょうか。
ストレスと血圧の関係について詳しく解説します。
参考:日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」(PDF)
血圧上昇には、ストレスと自律神経の関係が影響しています。ストレスに対抗する生体反応として、自律神経のうち交感神経が優位な状態となり、血流が増加することで血圧上昇につながります。
また、活性酸素によるストレスも血圧上昇の原因の1つです。ストレスを受けるとコルチゾールなどの副腎皮質ホルモンという物質が分泌されます。副腎皮質ホルモンが酵素によって分解される過程で体内の活性酸素が増え、血圧が高くなるとされています。
ストレスと高血圧は密接に関係しており、ストレスに弱い性質があると、慢性的な高血圧状態に陥りやすいといえるでしょう。
高血圧のうちストレスとの関連が強いのは、診察室外の日常的な環境下で計測すると血圧が高くなる仮面高血圧です。
仮面高血圧は、通常の高血圧よりも死亡リスクが高いことが研究で示されています。そのため、ストレスに起因する高血圧には注意が必要です。自動血圧計を活用して、昼間の血圧変化を把握し、ストレスによる血圧上昇をチェックすることが大切です。
仮面高血圧の代表例として、仕事中のストレスにより血圧が上昇する職場高血圧があります。健康診断で異常がなくても、勤務中に慢性的な高血圧状態が続き、病気の発症につながる場合があります。
とくに、仕事の裁量範囲が狭い状態はストレスがたまりやすいとされています。ある研究では、軽度の高血圧の男性では、仕事の裁量範囲が狭いとさらに拡張期血圧が高くなる恐れがあることが示されています。収縮期血圧に異常がないからといって、見過ごさないようにしましょう。
高血圧を予防するために、ストレスに強くなるにはどうすればよいのでしょうか。ストレスの感じやすさには、性格の傾向が影響しています。以下のように、タイプA性格と呼ばれるせっかちで挑戦的、仕事熱心な人はストレスがかかり、血圧が上がりやすいでしょう。
タイプA性格に当てはまる場合は、考え方や仕事への姿勢を見直すとストレスが軽減し、高血圧の予防につながるでしょう。3つの対処方法を紹介します。
タイプA性格の人は、仕事熱心で多くの業務を抱えていることが多いでしょう。しかし、「仕事をしなければならない」という義務感から、ワーカホリックに陥ってしまうことがあります。
ワーカホリックは、仕事以外の時間を犠牲にして仕事だけに取り組む状態です。仕事熱心な状態とは少し異なり、中毒に近い状態とされます。元気に働けるうちは良いのですが、疲弊して動けなくなるとバーンアウト(燃え尽き症候群)に陥る可能性があります。
ワーカホリックに陥らないようにするには、仕事のやりがいについて再確認することが大切です。具体的な方法としては、ジョブ・クラフティングがおすすめです。
自分の仕事がどのように役立っているか、自分の強みをどう生かせるかなどを整理し、日々の業務の意味を再確認します。働く意欲を表すワークエンゲージメントを高め、仕事を「しなければならない」から「したい」に変えていく効果があります。
タイプA性格の人は、ストレスがたまっていることに気づかず、無理して働くことが少なくありません。慢性的なストレス状態でも、「自分は強いから大丈夫」と働き、突然大きな病を発症する可能性があります。
とくに、仕事熱心で競争心が強い人は、周りに負けたくないという一心から、無理してでも働きがちでしょう。タイプA性格に当てはまる場合は、一度ストレスがたまっていないか振り返ることが大切です。
競争心が強く、負けず嫌いな性格だと、仕事に対して完璧主義になりやすいでしょう。多忙な業務に疲れたり、慣れない仕事に不安を感じたりしても、「弱音を吐いてはダメだ」と押し殺すことがあるかもしれません。
また、自分に厳しいと、周りにも厳しくなってしまうことがあります。部下のレスポンスが遅かったり、責任感のない発言が気になったりするなど、周囲の言動にイライラしてしまうこともあるでしょう。
仕事において、自他ともに厳しくあるのは大切ですが、厳しすぎると自分を苦しめることになります。「疲れた」「不安だ」「イライラする」など自分の素直な気持ちを認めるよう意識するとよいでしょう。
高血圧とストレスは密接に関係していますが、健康診断をはじめとした病院で計測する血圧からは判断できないことがあります。また、職場に限定されたストレスは、拡張期血圧だけを上昇させるケースもあり、「上の血圧は正常だから大丈夫」と見過ごしてしまうかもしれません。
ストレスと高血圧の関係性を正しく理解し、ストレス性の高血圧を発見して適切な対処をとりましょう。