

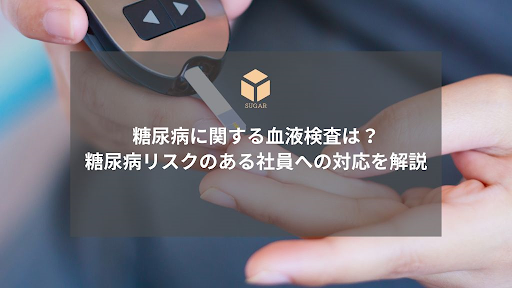
糖尿病は合併症や体調不良を引き起こし、社員の業務効率を低下させる可能性があります。そのため、企業として発症や症状の悪化を未然に防ぐことが大切です。
糖尿病の予防には、健康診断での血液検査結果をもとに、基準値を上回っていれば再検査をすすめることが求められます。しかし、基準値を上回っていても「体調に問題はないから大丈夫」と考えて見過ごす社員も少なくありません。
また、基準値を上回らない高めの数値にも発症のリスクがあります。そのため、糖尿病予防のためには、血液検査からわかるリスクを正しく理解することが求められるでしょう。
本記事では、糖尿病に関係する血液検査の項目と、発症リスクのある社員への対応を解説します。糖尿病の社員への組織的な対応策についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
糖尿病をはじめとした生活習慣病は、定期的に実施される健康診断結果から発症リスクを見極めます。糖尿病かどうかを疑うとき、健康診断結果をどのようにみればよいのでしょうか。血液検査項目の見方を中心に解説します。
参考:日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2019」(PDF)
糖尿病に関係する血液検査項目は、血糖値とHbA1cの2つの項目です。血液検査結果だけで糖尿病とは断定されませんが、2つの項目が基準値を上回っているかどうかを参考にします。
血糖値とは、血液中にブドウ糖が含まれる割合のことを指します。食事をとった後に血糖値が上昇し、インスリンが分泌されると正常な値に下がるというのが健康な状態です。
しかし、糖尿病では、インスリンがうまく作用せず、血糖値が下がらない状態が続いてしまいます。そのため、血糖値が高いことは糖尿病かどうかを示す指標といえます。
糖尿病とされる血糖値の基準は、日本糖尿病学会が定めるガイドラインで以下のように決められています。
※ブドウ糖負荷試験:空腹時血糖よりも検査を行う条件を一定にし、より正確な血糖コントロールができているかを測る方法。
また、空腹時血糖値が126mg/dL未満であっても、100~109mg/dLは正常高値、110~125mg/dLは境界型高血糖に分類されます。正常高値や境界型高血糖も糖尿病に移行するリスクがあるため、精査やフォローなどの経過観察が必要です。
HbA1c(ヘモグロビンA1c)とは、過去1~2カ月の血糖値の平均を示す指標です。日本糖尿病学会のガイドラインでは、6.5%以上だと糖尿病診断の条件の一つを満たします。
血糖値は、採血した時点での値を測るので、計測前の食事や運動の影響を受けやすいという欠点があります。しかし、HbA1cは、直近1〜2ヶ月の血糖値の平均を示す推移のため、健康診断や採血検査の前日や当日の影響を取り除いて測定できます。
血糖値について万全を対策をするなら、血糖値だけでなくHbA1cの値も合わせて把握しておくことが重要です。
糖尿病かどうかは、血糖値とHbA1cの値をもとに判断することが一般的です。両方の値の高低や貧血の有無によって判断基準が異なります。
血糖値およびHbA1cのいずれも高血糖値である場合、糖尿病に該当する可能性が高いといえます。ただし、別日に行った検査でいずれも基準値を上回っている必要があり、1回の健康診断結果だけでは判断できないことがあります。
いずれも基準値を上回っている場合、医療機関の受診をすすめて再検査を行うことが望ましいでしょう。
血糖値だけが高く、HbA1cは正常値だという場合、診断には糖尿病症状の有無が重要です。口の渇きや体重低下などの典型的な糖尿病の症状がみられる場合、糖尿病と診断される可能性が高いでしょう。
また、空腹時血糖値が126mg/dL未満である場合も注意が必要です。境界型高血糖(110~125mg/dL)の範囲にあるときには、ブドウ糖負荷試験による再検査が推奨されます。空腹時血糖値は正常でも、ブドウ糖負荷試験での血糖値が高くなるというケースがあるためです。
血糖値は正常でも、HbA1cだけが高い場合、食後に高血糖状態となっていることが疑われます。1カ月以内に、血糖値の測定を含めて再検査をすすめましょう。HbA1cが6.5%未満でも、5.6~6.4%の場合はブドウ糖負荷試験を行うことが推奨されています。
また、鉄欠乏性貧血という鉄分が足りない人に起きやすい貧血の人は、ヘモグロビンの総数が少ないために、血糖値は正常値にも関わらずHbA1cのみ高くなることがあります。
いずれの場合でも、糖尿病や貧血の治療を行う必要性が高いため、医療機関を受診して精査することが好ましいです。
溶血性貧血の人は血液中のヘモグロビンの寿命が短く、糖尿病であるにもかかわらず、HbA1cの値が低くなることがあります。
HbA1cは、直近1〜2ヶ月に作られたヘモグロビンのタンパク質に血糖が結合している割合を表すため、ヘモグロビンの寿命が短いと古いヘモグロビンが代謝されてHbA1cの値も低くなってしまいます。
溶血性貧血などの遺伝性の貧血などがある場合は、HbA1cではなく、グリコアルブミン(GA)の値を参考にするとよいでしょう。
グリコアルブミンの基準値は、11~16%です。また、グリコアルブミンとHbA1cの換算は以下の計算式で求められます。グリコアルブミンが健康診断の項目に含まれていない場合でも、糖尿病リスクの判断基準として役立ちます。
HbA1c=GA/4+2
糖尿病は合併症を引き起こしやすく、がんや脳梗塞につながるケースも少なくありません。また、血糖コントロールが難しく、高血糖もしくは低血糖状態による症状から、生活や仕事に支障をきたすことがあります。具体的には、どのような症状がみられるのでしょうか。
高血糖状態が続くと、次のような合併症を引き起こす可能性があります。
高血糖状態は、全身の血管に負荷がかかるため、動脈硬化が進行します。そのため、血管が詰まりやすく、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こします。脳梗塞により、脳血管性認知症の発症につながることもあるでしょう。
また、血糖値が高いと白血球や免疫の働きが弱くなり、尿路感染や歯周病などの細菌感染を起こしやすくなります。さらに、高血糖状態を改善するために分泌されるインスリンの量が多くなると、細胞を増殖させてがんの発症リスクを高めることもあります。
糖尿病の典型的な症状として、高血糖状態に伴う口の渇きや多飲、頻尿などがあります。血液中の水分量を増やして血糖値を下げようとするため、口が渇いて水分を多くとるようになるためです。そのため、こまめに水分をとらないと脱水を起こす危険性もあります。
また、ブドウ糖を体内にうまく取り込めず、エネルギー不足になることから倦怠(けんたい)感が生じることも典型的な症状です。身体がだるく、仕事の効率が上がらないということが起きやすいでしょう。
血糖値を下げる薬が効きすぎてしまい、低血糖状態に陥ることがあります。低血糖状態になると起こるのが、不安や動悸、息切れなどの症状です。
血糖値を上げるために、体内にたまっているブドウ糖を放出しようとします。このとき、アドレナリンが分泌されるため、交感神経が働いて緊張したときのような症状がみられることがあるのです。
重度な低血糖状態に陥ると、意識障害を起こすケースもあります。取り返しのつかない状態にならないよう、血糖値を適切にコントロールできているかどうかをチェックすることが大切です。
職場に糖尿病やそのリスクがある社員がいる場合、企業としてどのように対応すればよいのでしょうか。業務面で注意すべきポイントについて解説します。
糖尿病の社員に対するサポート方法については、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:糖尿病で就業制限を受けたら?企業側がサポートすべき5つのことを解説
糖尿病の社員に対しては、一人で長時間作業させることを控えた方がよいでしょう。低血糖または高血糖状態では、重篤な場合に意識障害に陥る可能性があるからです。
誰かがいる環境で作業してもらうか、定期的に様子をチェックできるような仕組みをつくっておく必要があります。周囲に誰もいないという状況が長時間続くことは避けた方がよいでしょう。
糖尿病の治療においては、いかに悪化や合併症を防ぐかが重要です。症状の悪化や合併症につながる労働環境や働き方を見直し、配慮することが求められます。
とくに、長時間労働や夜勤は悪化の原因になるとされています。不規則な勤務体系で食事習慣のリズムが乱れ、低血糖のリスクがあるからです。また、長時間労働で適切なタイミングで水分がとれず、脱水を引き起こすこともあります。
企業としては、リスクのある社員が血糖コントロールを良好に保てているかを把握し、必要な配慮を行うことが大切です。たとえば、以下のような配慮を行うとよいでしょう。
糖尿病は、治療につながっても8%の人が中断してしまうとされています。とくに仕事に就いている男性に多く、中断の理由として「仕事の忙しさ」が1位ということがわかっています。忙しさを理由に中断しないよう、通院のための時間を確保する仕組みづくりが必要です。
また、「体調が悪くない」という理由での中断率も多い傾向にあります。自覚症状がなくても、血糖値が高いと糖尿病リスクがあることを、社内に向けて説明していくことが大切です。
参考:日本糖尿病・生活習慣病ヒューマンデータ学会「糖尿病受診中断対策マニュアル」(PDF)
糖尿病に関する血液検査結果の項目は2つあり、それぞれの高低によって対応が少し異なります。「HbA1cは高いけど、血糖値は低いから大丈夫」と誤解する可能性があり、正しい知識を伝えていくことが大切です。
血液検査項目と糖尿病の診断基準の関係を理解し、社員の糖尿病の発症や悪化を防いでいきましょう。