

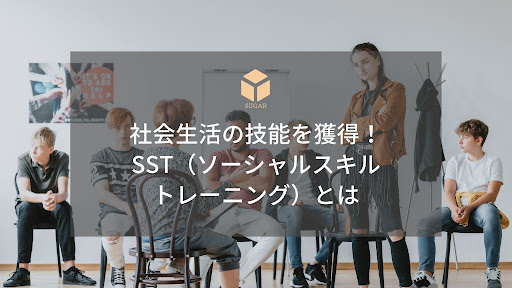
社会生活の技能を獲得する、SSTというトレーニングが存在することをご存じでしょうか。SSTとは、Social Skills Training(ソーシャルスキルトレーニング)の略で、社会生活技能訓練とも呼ばれます。
「社会生活の技能」や「ソーシャルスキル」という言葉も、あまりなじみがないかもしれません。
今回の記事では、SSTや関連する言葉について、基礎からわかりやすく解説します。最後までお読みいただくことで、社会生活で必要となるソーシャルスキルの獲得の仕方がイメージできるようになります。
SSTとは、どのような人に効果が見込まれるトレーニングなのでしょうか。「社会生活の技能」や「ソーシャルスキル」が不足するとどのような困りごとが生じるのでしょうか。
SSTの対象者をイメージしやすくするために、職場でありがちな、苦労している人たちの例を取り上げます(取り上げた例はイメージしやすいよう誇張したものであり、実例によるものではありません)。
関連記事:上司とのコミュニケーションは難しい…改善するメリットやコツを解説
Aさんは会話が苦手です。朝出勤したときも、夕方退勤するときも、あいさつはしていません。
仕事はすべて受け身です。わからないことがあっても質問することができず、机に向かって座ったまま時間だけが過ぎていくことがあります。上司から報連相を行うように言われていますが、どう話せばよいのかわからず悩んでいます。
職場の上司も、Aさんからの発信がなく仕事の状況がわからないので困っています。
Bさんは、わからないことは質問するように言われていたので、急ぎではありませんでしたが、商談中の上司に質問しにいきました。上司は不愉快な顔で、後にするようジェスチャーを出しましたが、Bさんは気づかず、「空気を読め」と叱られてしまいました。
翌日Bさんは名誉挽回しようと、2時間早く出勤し職場の掃除をしていました。きっとほめてもらえると思っていましたが、「勝手なことをするな」と逆に叱られてしまいました。なぜ叱られたのか、Bさんはわかりませんでした。
同僚との関係性も良くないようで、上司のもとには、会話をするときの距離が近すぎる、仕事中に雑談が多いといったBさんについての苦情が寄せられています。
責任感が強く、職場からとても頼りにされているCさん。いつも仕事が集まってきます。毎日最後まで職場に残って仕事をしているにもかかわらず、仕事はたまる一方です。
仕方がないので、休みの日も家に仕事を持ち帰って、こっそり仕事をしています。プライベートの予定はすべてキャンセルし、睡眠もとれません。「なぜ私ばかり」と思う毎日が続いています。
Cさんは半年以上、有給休暇を取得していません。残業時間は突出して過労死ラインを超えており、労働組合が調査を始めました。上司は「早く帰れと言っても帰らない。しなくていい仕事をしている」と困っています。
統合失調症を発症し、休職していたDさん。症状も落ち着き、復職できるようになりました。久しぶりに職場に行くので、上司や同僚にどうあいさつをしたらよいのか悩んでいます。
これまでは車で通勤していましたが、服薬時に眠気が出るため、復帰後は電車とバスを使って通勤することになります。地方に住むDさんは、今まで電車とバスを利用したことがありません。
上司は、休職前にコミュニケーション面でDさんが苦労していたことを心配しています。同じことを繰り返さないように、復職までにコミュニケーション上のスキルを学んでほしいと考えています。
職場でありがちな、苦労している人たちの例を見てきました。「報連相や質問をしない。空気が読めない。表情やしぐさ、距離感がわからない。断れない。頼めない」という問題が生じていました。
これらが「社会生活の技能」や「ソーシャルスキル」が不足している状態の一例です。
それでは、「社会生活の技能」や「ソーシャルスキル」を身につけるソーシャルスキルトレーニング(SST)について次に説明します。
SSTは、精神科病院に長期入院していた人を対象に始められました。退院して地域に社会復帰した後に、社会に適応して生活するために必要な、情緒的表現や対人技能を教えることが目的でした。
自分の気持ちや必要なことを他の人に伝えるコミュニケーションスキルだけではありません。服薬や病気についての自己管理能力や、自立した生活を送るための日常生活技能も、広義のスキルとして含まれています。
SSTが20世紀後半に日本に伝わって以降、対象とする領域は、職業生活の分野や児童教育の分野にも広がっています。
産業・就労支援の分野では、業務を遂行するための円滑なコミュニケーション能力という意味で「ソーシャルスキル」が使われます。
また、職業準備性(働く上で最低限備わっていないといけない生活面の能力も含めた能力)の意味で使用されることもあります。
SSTは、精神科医のリバーマンが、精神障害者の治療やリハビリのために開始したトレーニングです。社会学習理論、行動療法、認知療法、集団療法などを基盤とした認知行動療法の理論に基づいています。今では効果が広く認められ、多くの分野で応用されています。
改善したい行動を設定し、行動する場面を再現したロールプレイを行うことで、実際の場面でも自信をもって望ましい行動がとれるようになります。
SSTは、少人数でのグループで、参加体験型のプログラムとして行われます。
最初にアイスブレイクや、SSTのオリエンテーションを行った後、その日のテーマについて話し合います。
たとえば「質問」をテーマにすると、なぜ「質問」が大切なのか、「質問」で困った経験はあったか、どうすればうまく「質問」できるかなどについて話し合います。
次に、テーマに沿ったロールプレイを行います。場面設定は、できるだけ取り組みたい課題や目標に沿ったものにします。まずはリーダーが見本を見せ、観察者は「良かった点」や「さらに良くする点」について発言します。
ロールプレイのイメージをつかめたら、参加者からロールプレイの実施者を募ります。参加者が取り組みたい場面設定を改めて行った後、ロールプレイを行い、できるかぎりプラスのフィードバックを行います。必要に応じて、日常の場で実践できることを宿題にします。
参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者職業総合センター職業センター実践報告書 平成9年9月 No.2 SSTを活用した精神障害者に対する職業指導(1)‐職業レディネス指導事業の実践から‐」(PDF)
参考:障害保健福祉研究情報システム(DINF)「生活技能訓練(Social Skills Training:SST)」
参考:一般社団法人 日本集団精神療法学会「リレーコラム『集団精神療法のさまざまなかたち』 No.04 ~SST編①~ 技法(SST)の紹介 SSTの技法における『ささやかさ』」
SSTはさまざまな分野で応用されており、分野ごとに進め方やテーマの内容が工夫されています。ここからは、就労・産業分野で設定されるテーマを紹介します。
日常生活や通勤に必要なソーシャルスキルを扱います。
「遅刻しそう」「主治医に症状を伝えたい」「バスの乗り方がわからない」「友人との長電話を切れない」「お酒の誘いを断れない」などのテーマが考えられます。
社会生活を扱うSSTは、精神科病院のデイケアやグループワークを行う教育施設などで体験することができます。
「報告する」「質問する」「相談する」「断る」「連絡する」といった仕事で必要となるテーマを扱います。上司のタイプや職場の風土など、設定する場面によって、同じテーマでもロールプレイの難易度が変わります。
職業生活に特化したSSTとして、JST(職場対人技能トレーニング:Job Related Skills Training)が開発されており、就労支援機関や、地域障害者職業センターで受講することができます。
職場で苦労している人の中には、ソーシャルスキルの知識や経験がないまま、社会人になってしまった人も少なくありません。SSTでは、ロールプレイを通じて、望ましい行動を理解して実行することで、社会に適応できるスキルを身につけます。
新社会人に対する導入教育としてもSSTは活用できます。機会があれば、SSTを実施している機関に足を運び、見学してみてはいかがでしょうか。