

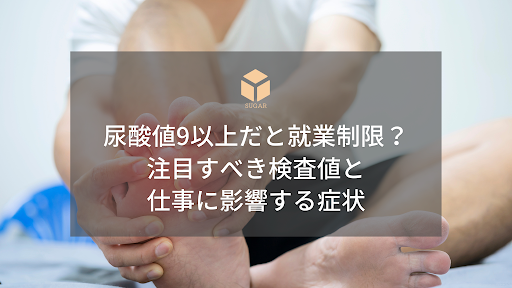
尿酸値が高い状態(高尿酸血症)が続くと、激痛を伴う痛風発作や尿路結石を発症しやすくなり、仕事はおろか日常生活にも支障をきたしてしまいます。
また、それだけでなく尿酸値が高い状態を放置してしまうと、脳卒中・心筋梗塞・腎機能の低下のリスクが高くなり、長期間、職場離脱する可能性が出てきます。
本記事では、尿酸値の正常値や高尿酸血症の症状、痛風発作になりやすい人の特徴を解説しています。痛風発作・尿路結石・合併症を社員が発症することによる企業の機会損失を防げるよう、ぜひご確認ください。
実は、尿酸値の検査は定期健康診断(労働安全衛生法)の必須項目には入っていないため、そもそも定期健康診断で検査するかどうかは企業によって異なります。
人間ドックを受けた場合は尿酸値も検査してもらえるため、企業によっては人間ドックを推奨し尿酸値を把握しているところもあります。
では、尿酸値がどんな値だと改善が必要なのかについて説明していきます。
健康診断の血液検査の一覧の中にある「UA」という表記が尿酸値です。男女問わず尿酸値が7mg/dlを超える場合は、高尿酸血症と診断され受診が必要です。
一般的には、尿酸値が8mg/dl〜9mg/dl以上になると、さらに痛風発作の危険が高まり、早期の治療が推奨されます。
近年では食事の欧米化により、高尿酸血症の患者は年々増加しており、痛風の初発年齢は30歳代に多いことが明らかになっています。
参考:一般社団法人日本痛風・尿酸核酸学会「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第3版」
高尿酸血症の症状は動くと激痛を伴うものが多く、日常生活が制限され、仕事も休まざるを得ない状況になってしまいます。
その代表的な症状3つについて解説していきます。
高尿酸血症といえば、代表的な症状は痛風発作ですが、足の親指の付け根に風が吹いただけでも激痛が伴うくらい痛いと表現されます。
出現する部位は、足の親指の関節だけでなく、足の甲、アキレス腱(けん)の付け根、手や膝の関節に痛みを感じる人もいます。
痛風発作は、環境要因(プリン体の過剰摂取・飲酒・肥満など)が大きく影響しており、内服治療に加え生活習慣の見直しが必要です。
高尿酸血症が長期間になるほど、痛風発症のリスクは高くなることもわかっており、早期治療がすすめられます。
尿路結石は、腎臓に結晶となった尿酸がたまり、結石ができると背中に痛みが生じます。
さらに、結石が尿管や膀胱(ぼうこう)に移動するとその部分で炎症を起こします。尿管などの細い部分に詰まると激しい痛みが生じ、石が外に排出するまで痛みが続きます。
尿路結石の患者は世界的に増加傾向にあり、原因としては食事や生活様式の欧米化が起因しています。
よって、尿路結石症の予防のためには、食事療法、生活指導は必須となります。
痛風自体で亡くなる人はいません。しかし、尿酸値が高い状態が長期間になると動脈硬化が促進され、脳卒中・心筋梗塞・腎機能障の低下などの合併症のリスクが高くなります。
合併症が発病してしまうと、日常生活に制限が生じるため、必然的に仕事にも影響を及ぼします。
脳卒中の症状の中には、身体麻痺・言語障害・認知機能障害などがあり、元の職場への復帰が困難な場合も考えられるため、高尿酸血症を放置することはかなり危険だといえるでしょう。
参考:一般社団法人日本痛風・尿酸核酸学会「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第3版」
尿酸値が高い原因は、遺伝も一つの影響として考えられますが、多くの場合食生活や生活様式の欧米化が進んだことによるものです。
では、どんな人が痛風になりやすいのか3つの特徴を挙げて説明していきます。
アルコールを飲むと体内の尿酸値が上がることがわかっています。
世間一般では、ビールにプリン体がとくに含まれているといわれているので、プリン体offやプリン体0のお酒なら大丈夫と思っている方がいます。
しかし、アルコールを身体の中に入れている時点で尿酸値が上がってしまうので、結果高尿酸血症のリスクが上がります。
高尿酸血症を指摘された場合は、お酒の適量を守るようにしましょう。
激しい運動をすると尿酸が増え、尿酸の排泄機能が低下することがわかっています。
ただし、適度な運動(歩行・ジョギング・サイクリングなど)は肥満を解消し、高尿酸血症の予防につながります。1回10分以上の運動を、1日合計30~60分程度行うことが推奨されています。
内臓系の食物や魚卵、乾物には多くのプリン体が含まれています。プリン体は主に肝臓で分解されて尿酸となります。
尿酸は一時的に体内にため込まれた後に、尿や便として排泄されますが、大量に摂取した場合は、高尿酸血症となる可能性があります。
プリン体を多く含む食材には下記のようなものがあります。
| プリン体の量(100g当たり) | 豊富に含まれる食材 |
| 極めて多い(300㎎~) | 鶏レバー、干物(マイワシ)、白子(イサキ、ふぐ、たら)、あんこう(肝酒蒸し)、太刀魚、健康食品(DNA/RNA、ビール酵母、クロレラ、スピルリナ、ローヤルゼリー)など |
| 多い(200~300㎎) | 豚レバー、牛レバー、カツオ、マイワシ、大正エビ、オキアミ、干物(マアジ、サンマ)など |
| 中程度(100~200㎎) | 肉(豚・牛・鶏)類の多くの部位や魚類などほうれんそう(芽)、ブロッコリースプラウト |
| 少ない(50~100㎎) | 肉類の一部(豚・牛・羊)、魚類の一部、加工肉類などほうれんそう(葉)、カリフラワー |
| 極めて少ない(~50㎎) | 野菜類全般、米などの穀類、卵(鶏・うずら)、乳製品、豆類、きのこ類、豆腐、加工食品など |
参考:一般社団法人日本痛風・尿酸核酸学会「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第3版」
また、果糖やキシリトールも代謝される時にプリン体が生じるため、甘味飲料やジュースは控えることをすすめます。
逆にコーヒー、チェリー、ビタミンC、乳製品(特に低脂肪)、食物繊維は痛風のリスクを下げることがわかっています。
参考:高尿酸血症 | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)
参考:アルコールと高尿酸血症・痛風 | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)
参考:一般社団法人日本痛風・尿酸核酸学会「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第3版」
職場において、上司・人事がすべき高尿酸血症の社員への配慮について3つの方法を紹介します。
尿酸値が高い社員がいる場合は、健診結果を持って産業医もしくはかかりつけ医に相談し、会社としての対応を考えていきましょう。
就業上の措置(就業制限の有無)については産業医の意見をもとに勘案するため、就業上の措置が必要なのかどうかを産業医に相談してみましょう。
※産業医がいない事業所は、産業保健総合支援センターに相談することも可能です。
尿酸値が7mg/dl以上の場合は健康管理を担っている担当者や上司から受診をすすめましょう。
高尿酸血症は放置すると仕事にも支障をきたす危険な病気につながります。
企業によっては、受診した結果まで知らせる仕組みをつくって、社員の健康管理を徹底しているところもあります。
※ただし、尿酸値については法定項目ではないため取り扱いには衛生委員会などで協議する必要があります。
高尿酸血症の改善・再発予防として、生活習慣の見直しは必須となります。
保健指導を通し社員教育をすることで、ヘルスリテラシーを向上させ、予防することが再発を繰り返さないためにも重要といえます。
その際に利用していただきたいのが、医師や保健師による保健指導です。
中には病院や産業保健総合支援センターで保健指導(栄養指導)をしてもらえるので、尿酸値が高い社員がいる場合は活用してみてください。
参考:産業保健総合支援センター(さんぽセンター)| JOHAS(労働者健康安全機構)
尿酸値が高くても自覚症状がない人が多いのですが、痛風発作や尿路結石の症状が発症してしまうと数日は働くことができず、会社の機会損失につながります。
よって、40代以上の方には人間ドックを推奨し、尿酸値を把握することも一つの手段です。
また、40代未満の方は定期健康診断で検査するかどうか、ぜひ産業医に相談し衛生委員会などで協議してみてください。
尿酸値が高いくらいで…などと思わず、受診を促したり、必要であれば保健指導をしてもらうなど適切な対応をすることをおすすめします。
SUGARでの尿酸値に対する就業措置についての情報は以下をご参照ください。