

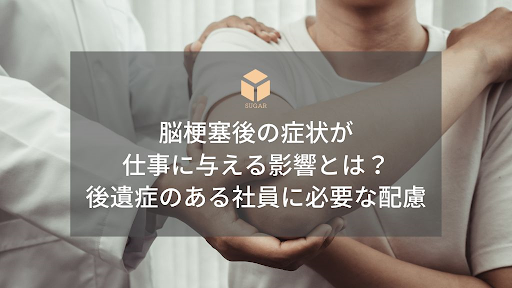
脳卒中は日本人の死因第3位となっていますが、医療の進展などに伴い、その死亡率は低下しています。脳卒中の中で、過半数を占めるのが脳梗塞という病気です。
脳梗塞と聞くと、手足の麻痺など大きな後遺症が残るイメージがありますが、働く世代の患者では、治療やリハビリテーションにより仕事ができる状態まで回復が望めることも多いといわれています。そのため、職場復帰が可能な例も少なくありません。
しかし、脳梗塞の症状が残ってしまった場合、復職後に以前と同じように働けず戸惑う社員も多くいます。
この記事では、脳梗塞後の症状が仕事に与える影響と、症状が残ってしまった社員に必要な配慮について解説していきます。
参考:厚生労働省 脳卒中 | e-ヘルスネット (mhlw.go.jp)
脳梗塞とはどんな病気か、また脳梗塞後の症状にはどんな症状があるか解説します。
脳梗塞は、脳の動脈が何らかの原因で閉塞したり細くなったりして、脳の血液の循環に障害をきたし、十分な酸素やエネルギーが供給されず脳細胞が壊死(えし)してしまう病気です。
一度壊死した脳細胞は元に戻ることはありません。血管が詰まる原因によって主に3タイプに分類することができます。
脳梗塞の主な治療と経過
脳梗塞の症状は突然現れます。主な治療法は、血管内部に詰まった血栓を溶かす薬物療法とカテーテルを血管に入れて血栓を直接除去するカテーテル治療です。
また、日常生活や職場復帰のために、発症後早期からリハビリテーションが開始されます。障害の程度によっては、退院後も継続して行う必要があります。
脳梗塞の経過は、主に次の3つの段階に分けることができます。
脳梗塞後に残る症状
脳梗塞発症後に、運動機能や言語機能の低下が残る場合があります。一般的に、運動機能は発症から3〜6カ月までに顕著に回復し、以降はあまり変化が見られなくなります。言語機能は1年を経過すると徐々に回復する傾向があります。
手足の麻痺など目に見える症状のほか、一見してわかりづらい高次脳機能障害が残ることもあります。
高次脳機能とは、記憶、学習、思考、判断などの認知の過程と情動についての機能の総称です。脳梗塞により脳に損傷を受け、認知機能に障害が起きた状態を高次機能障害といいます。
そのため、脳梗塞による症状として、注意力・記憶力の低下、遂行機能障害などが生じることがあります。
参考: 一般社団法人脳卒中学会 脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕(PDF)
厚生労働省 事業場における治療と仕事の 両立支援のためのガイドライン(PDF)
人によっては脳梗塞による症状が残る場合もあり、就業上の措置が必要になることがあります。
病名を公表するか、また残存した症状を職場に伝えるか、多くの人が悩む事柄です。
しかし、企業には社員に対する安全配慮義務があるため、社員には復職にあたり、主治医に症状の有無や程度、職場で配慮したほうがよい事項について確認し、情報共有してもらうことが大切です。
職場でできる配慮について、以降で詳しく説明します。
脳梗塞によって生じる症状には、目に見えてわかりやすいものもあれば、記憶力や集中力の低下など一見してわかりづらいものがあります。
症状によって、注意すべきことや周囲ができるサポートは異なるため、個別の対応が必要です。症状と対応方法の例について以下で説明します。
軽度の片麻痺が残ってしまった社員が復帰する場合、特定の動作や書字、両手の作業が難しいなど、仕事に影響する動作上の困難があります。どのような業務であれば行えるのか、どのようなサポートがあれば効率的に業務を行えるか検討することが大切です。
病院のリハビリでは、実際の業務を行えるか評価することは難しいため、リハビリ出勤や、短時間勤務から開始するなど段階的な職場復帰を検討することも必要でしょう。
感覚障害には、大きく分けて感覚過敏や感覚鈍麻(どんま:感覚が鈍くなること)、異常感覚があり、手足のしびれや痛み、感覚の鈍さがよくある症状です。
精密な作業は難しく、粗大なものを取り扱う作業などへの変更が求められます。また、温度感覚が鈍ることもあり、熱いものを取り扱う作業には注意が必要です。
客観的にはわかりにくい症状ですが、本人が症状の程度について一番理解しているため、職場復帰前に症状の程度について本人とよく話し合い、対応を検討しましょう。
注意力や集中力の低下がある場合、小さなミスを繰り返してしまうことがあります。短い時間で完結する業務から開始し、都度休憩を取るなど配慮しましょう。
記憶障害がある場合は、手順書を作成する、メモを取ってもらうよう声掛けを行う、一つの作業に集中してもらうなどの配慮が大切です。
遂行機能障害には、実施すべき業務の優先順位が付けられないなどの症状があり、どの順番で仕事を行うか明確に指示してあげることが望ましいでしょう。
脳梗塞発症後、定期的な通院や再発予防のための服薬治療は生涯にわたり必要となる可能性があります。また、脳梗塞後の症状回復のため、リハビリを継続する人もいるでしょう。
そのため、社員より通院頻度や服薬に伴う副作用、その程度について情報提供してもらうことが望ましいです。社員より申し出があった場合は、企業は必要に応じて通院への配慮が必要です。
脳梗塞による症状の程度によっては、高所作業や重機操作など危険を伴う作業の継続は難しいことがあります。また、特に症状や後遺症がない場合でも、再発のリスクを考慮して、安全を確保するための措置を講じる必要があります。
企業は、産業保健スタッフと連携するなどして、どこまで対応できるか、本人が可能な仕事はどのレベルかを整理し、配置転換を含めた対応についても考慮することが望ましいでしょう。
参考:厚生労働省 令和3年3月改訂版. 企業・医療機関連携マニュアル. 事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(PDF)
脳梗塞後の社員が職場復帰する際は、脳梗塞によって生じる症状をよく理解することが重要です。運動障害のようにわかりやすい症状もあれば、周囲がなかなか気付けない症状、本人も気付きにくい症状があります。
そのため、仕事と治療の両立を支援していくためには、職場の上司や同僚と症状について共有し、できる支援をみんなで考えていくことが大切です。
非医療職では認識しにくい症状については、主治医や産業保健スタッフなどの専門職に相談し、適切なアドバイスを受けることで周囲の理解を深めていきましょう。
脳梗塞後の症状に対する支援は、個別性が求められる複雑なケースもあるため、特定の職員に任せきりにせず、職場全体でサポートができるように心がけましょう。