

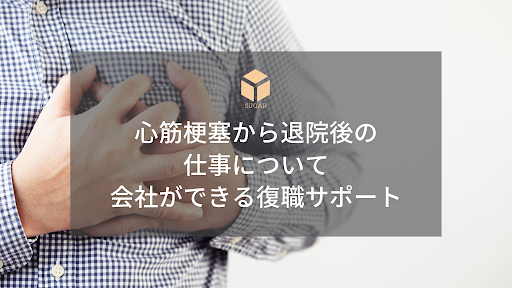
心疾患は命に関わる重大な病気です。心筋梗塞になった後、仕事を続けられるのか不安になる人も少なくありません。
心筋梗塞になった後は重症度や経過にもよりますが、会社が十分な配慮を行うことで仕事を続けることが可能です。この記事では、心筋梗塞で入院した社員が退院した後、仕事に復帰するために会社ができるサポートについて解説します。
心筋梗塞を含む心疾患は日本の死因第2位とされています。生活習慣病(高血圧症、糖尿病、脂質異常症、肥満)や喫煙、ストレスの影響が心筋梗塞の発症リスクを高めることが知られており、だれにでも起こり得る疾患といえます。
心筋梗塞は動脈硬化などの原因によって、心臓の血管にプラークや血栓などが詰まり、血液が流れなくなり、心筋が壊死を起こす病気です。
突然の、胸が締め付けられるような強い痛みや呼吸困難、胸の圧迫感が代表的な症状です。吐き気や冷や汗、顔面蒼白、肩から腕・胃のあたりの激痛(放散痛)といった症状を伴うことがあります。これらの症状が10分〜数時間程度続きます。
参考:厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト「狭心症・心筋梗塞などの心臓病(虚血性心疾患)」
心筋梗塞発症後は、できる限り早く治療を開始することが重要です。代表的な治療として以下の方法があります。
突然の発症から入院して、カテーテル治療や手術が行われる「急性期」の後、再発を防ぎ、以前の日常生活に戻るために重要なのが「回復期」です。回復期では、心臓リハビリテーションという有酸素運動を中心としたリハビリが開始されます。この心臓リハビリテーションは急性期終了後のリハビリ開始から通常5カ月程度実施され、患者さんは日常生活や仕事復帰に向けて準備をします。
参考:厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト「狭心症・心筋梗塞などの心臓病(虚血性心疾患)」
参考:一般社団法人日本循環器学会「冠症候群ガイドライン(2018 年改訂版)(PDF)」
参考:厚生労働省「事業場における治療と仕事の 両立支援のためのガイドライン(PDF)」
結論から言うと、心筋梗塞治療後の仕事復帰は可能です。病状や重症度、年齢によって経過や予後は異なってきますが、日常生活に復帰できるケースは多く、必要な配慮を行うことで長期的には復職できる人が多いとされています。
ただし、仕事の負荷が心筋梗塞の再発など病状に影響を及ぼす懸念もあり、病状と仕事の負担とのバランスを慎重に考慮しなければならないケースもあります。職場復帰に際しては適切な情報収集に加え、社員本人とよく話し合うことが重要です。
仕事復帰に関しては、心臓がどれだけ機能しているか、どれくらいの肉体労働であれば耐えられるか、運動負荷試験で検査を行います。仕事の強度が、個人の安全域(最大心拍数の70%以内)であることが復帰の目安です。
一般的に急性心筋梗塞なら7〜10日の入院期間となり、デスクワークであれば退院1カ月後、肉体労働であれば、心臓リハビリテーションが終了した半年〜1年後が復帰の目安といわれています。
デスクワークといえども、精神的ストレスが非常に強ければ心臓に大きな負荷をかけることもあります。心機能だけでなく、精神面や家族・会社のサポート状況も含めて復帰の時期は医師によく相談することが重要です。
心筋梗塞の社員が退院し、職場復帰を目指す際に担当者はどのようにサポートすればよいのでしょうか。退院後から復職前、復職後にわけて解説します。
急性期である入院中は、社員は職場と関わりを持つことが困難です。退院後は状況把握のため、速やかに診断名や病状を報告してもらいましょう。
また、治療内容や重症度によっては退院後すぐに復帰できるケースと長期のリハビリを要するケースがあります。復職までのだいたいのスケジュールを確認し、長期休養となった場合は休職に必要な情報を伝えて、社員が安心して休める環境を提供できるようにしましょう。
・社員に確認すること
上記の内容を主治医の診断書に記載してもらうよう、依頼しましょう。
・社員へ情報提供すること
復職前には、復職時期や復帰に向けた段取りを社員と互いに確認しましょう。企業には、社員が安全で働きやすい環境で仕事できるよう、必要と判断された就業上の措置を行う義務があります。
そのため、心筋梗塞の社員の復職が決まったら、安全配慮義務の観点から主治医に意見書を求めたり、産業医の判断を仰ぐことが必要です。具体的には、勤務時間短縮や在宅勤務、必要に応じて配置転換などが必要となるか社員とよく相談をしましょう。
必要な措置や配慮を主治医意見書(復職診断書)に記載してもらいましょう。
心筋梗塞の社員が復職した後は、定期的に管理職や産業保健スタッフを通してコミュニケーションを取り、勤務状況が問題ないか確認しましょう。また、長期の休職から復職した社員は今までどおりの仕事ができず、抑うつや不安を抱えている可能性があります。メンタルヘルスの配慮も忘れずに行いましょう。
もし、心身共に負担を感じている場合は、以下のような職場にある制度を上手に活用できるよう配慮を行い、社員が無理のない範囲で働けるように工夫することが必要です。
参考:厚生労働省「働く世代のあなたに 心疾患の治療と仕事の両立 お役立ちノート」(PDF)
参考:厚生労働省「事業場における治療と仕事の 両立支援のためのガイドライン」(PDF)
参考:労働契約法
社員が心筋梗塞で入院した場合、企業は診断名だけで「復職できない」「予後が悪い」と勝手に判断しないように気を付けましょう。退院後は、社員本人から治療方法や病状など正しい情報を取得し、社員が復職できるように早期からサポートすることが重要です。
また、重症度や業務内容によって、個別の対応が必要となります。サポートの過程では主治医からの情報や産業保健スタッフとの連携をうまく活用していくことが必要となります。
さらに、企業は心筋梗塞の再発予防のために受動喫煙の防止や心臓に負荷のかかる業務・作業環境を避けるなどの措置を講じることが求められます。
産業保健スタッフなどの専門職と連携しながら、病気と仕事の両立支援を行うための環境整備に努めましょう。