

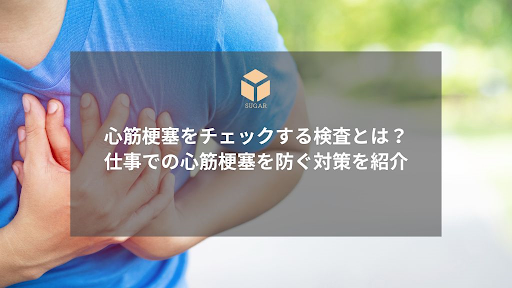
心筋梗塞は、胸部の激しい痛みが長時間続く原因になる心臓の病気です。死に直結する可能性もある疾患であり、治療が遅れると病状が悪化することもあります。
職場の健康管理を考える上では、心筋梗塞を予防するための適切な対処を行うことが大切です。
本記事では、心筋梗塞を早期に発見するための検査について解説します。心筋梗塞の症状と原因、職場において心筋梗塞を予防するための対策についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
生活習慣病の一つとされる心筋梗塞ですが、具体的にはどのような病気なのでしょうか。
冠動脈が何らかの原因で詰まり、心筋(心臓の筋肉)が壊死した状態が心筋梗塞です。
冠動脈とは、心筋に酸素や栄養を運んでいる重要な血管です。冠動脈が詰まる詰まると、心筋が壊死して全身に血液を送り出すことが難しくなってしまいます。
生命維持にもかかわる心臓の機能が適切に働かなくなる可能性がある、注意すべき疾患です。
心筋梗塞は、激しい胸の痛みが主な症状です。30分以上持続することが多く、一定時間持続することから不安や冷汗、脱力感などの症状も伴います。重い場合は失神に至るケースもあります。
心筋梗塞と同じく虚血性心疾患に分類されるのが、狭心症です。具体的には、動脈硬化が進行して冠動脈が細くなり、胸部の症状を引き起こす心疾患です。発症プロセスが似ており、狭心症から心筋梗塞に進展するケースもあります。
狭心症の状態では、血管が完全には詰まっていません。そのため、胸の圧迫感が生じるのは歩いているときや作業中に限定されることが多いです。激しい胸の痛みではなくても、心筋梗塞の前兆の可能性があるため、注意が必要です。
心筋梗塞は、冠動脈が詰まることで心筋に栄養が行き渡らなくなり、壊死してしまった状態です。具体的には、どのようなプロセスで心筋梗塞に至るのでしょうか。
心筋梗塞の主な原因は、動脈の血管が硬くなる動脈硬化です。動脈硬化は、血圧の上昇や脂質の摂りすぎにより、進行します。動脈硬化の進行により、血管の柔軟性がなくなると、血管の壁が厚くなります。その結果、血管が狭くなることで狭心症や心筋梗塞を引き起こすのです。
さらに、動脈硬化により血管の壁が傷つきやすくなり、何らかの物質が侵入しやすくなります。心筋梗塞が起こるのは、血管の壁の中にLDLコレステロールが侵入し、さらに対抗すべく免疫細胞が入り膨れることが主な原因です。
膨れ上がったところはアテロームとよばれるこぶになり、膨張して破裂すると血のかたまりができて血管を塞ぎます。そして、血管が詰まり、心筋梗塞を引き起こすのです。
動脈硬化の他にも、下記のような要因が心筋梗塞を引き起こす場合があります。
心筋梗塞は、高血圧や肥満などの生活習慣に関する乱れがリスクになることがあります。心筋梗塞の中で多い急性心筋梗塞のリスク要因として、以下の5つが挙げられます。
最近では、高血圧や喫煙率は低下している一方で、脂質異常症(高コレステロール状態)や耐糖能異常(高血糖状態)の割合が増加しています。社員の健康を考える上では、血圧の値や喫煙習慣以上にコレステロールや血糖値の値にも注意することが重要です。
参考:日本循環器学会「急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版)」(PDF)
生活習慣の乱れにより引き起こされる動脈硬化が、心筋梗塞の主な原因です。社員が心筋梗塞にならないよう、どのような検査を行い、予防の配慮を行うことが推奨されるか以降で説明します。
心電図とは、心臓が動くときに発生する電気を記録したもので、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患の診断に役立ちます。心筋梗塞が起こったときには、発症後数日から1カ月程度、以下のような典型的な波形の変化が生じます。
参考:トーアエイヨー「心筋梗塞の心電図と治療のポイント」(PDF)
心筋が壊死することで、血液中に特定の酵素が流出するため、血液検査により心筋梗塞かどうかを調べられます。以下のような項目から検査が可能です。
X線透視検査やエコー検査などの画像検査から、心筋梗塞の程度や発生場所を特定できます。心筋梗塞の診断や特定には、以下のような検査が用いられます。
心筋梗塞を発症し、病院に搬送される前に死亡してしまう割合は約40%と、見過ごすと危険な病気だといえます。心筋梗塞になってからでは遅く、早期に発見することが重要です。
早期発見のためには、健康診断で兆候を見逃さないよう、必要な検査を受けるよう社員に促すことが大切です。
また、管理職が率先して健康意識を高め、生活習慣を見直す意識づけを高めることも必要でしょう。
参考:上田恭敬(2016)「不安定狭心症に対する積極的治療で急性心筋梗塞の発症を予防する」(PDF)
心筋梗塞の予防には、原因となる動脈硬化を早期発見することが大切です。早期発見に有効な施策の一つが、職場で実施される健康診断です。血圧やコレステロール、中性脂肪、血糖値などの数値、心電図に異常所見がみられた場合、動脈硬化の可能性があります。
ただ、法律に定められた範囲での実施項目では、早期発見には不十分なこともあるでしょう。動脈硬化の程度を把握するためには、頚(けい)動脈エコー検査、血管内超音波検査、CT、MRIなどの精密検査が必要です。
一方で、健康診断で異常所見がみられても、精密検査を受けない社員がいるケースも少なくありません。受診率アップのため、受診費用を負担する制度を整備することが有効です。
制度を整備するには、労災保険の二次健康診断等給付制度を利用することがおすすめです。特定の健診項目に異常所見がみられる社員に対し、心エコー検査や頸部エコー検査などの精密検査に対して年1回までの助成が受けられます。
動脈硬化の予防には、生活習慣の改善が必要です。社員の健康意識を高め、健康リスクにつながる生活習慣を見直すことが予防につながります。
社内の健康意識を高めるためには、管理職などリーダー層が率先して健康を守るための行動を取ることが大切です。業務中の血圧測定や歩数計の着用など、健康に配慮した行動をとり、手本を示せるようにするとよいでしょう。
また、「血圧を正常値内にする」健康目標を立て、達成するとインセンティブがもらえるなどの制度も有効です。社員の健康行動に対する動機づけを高めるため、環境的な面に働きかける必要があるでしょう。
心筋梗塞は適切な治療を受ければ回復しますが、死に直結する可能性がある重大な心疾患です。社員の健康を守るためにも、動脈硬化を予防し、心筋梗塞を引き起こさないよう、日頃の対策とチェックが大切といえるでしょう。
心筋梗塞が起きる前には、作業時の胸の痛みや圧迫感など、何らかの前兆を経験している場合が多いことも特徴の一つです。職場全体で予防していくためには、身体に不調があれば、すぐに相談できる環境づくりが重要でしょう。