

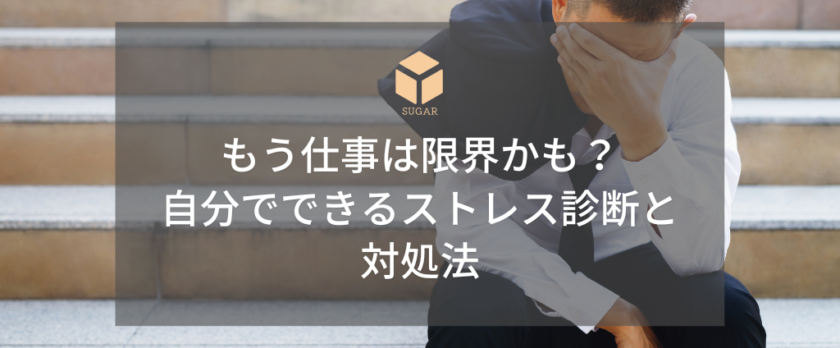
現代の日本では、仕事でストレスを感じる人が非常に多いといわれています。「ストレスの量を客観的な指標でチェックしたい」「ストレスにどう対処したらいいのだろう?」と考える人も多いのではないでしょうか。本記事を通して、ストレスを客観的に診断し、対処法を考えてみましょう。

厚生労働省の調査によると、現在の仕事や職業生活に関することで、強い不安やストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は54.2%という結果になりました。つまり、労働者の二人に一人は仕事に強いストレスを抱えながら働いていると考えられます。
では、自分の抱えるストレスをチェックしてみましょう。
参考:厚生労働省(2020)「労働安全衛生調査(実態調査)」
ストレス問題を考えるにあたって、まずは、ストレスの量や原因、抱えたときの表出傾向などに気付くことが大切です。その上で、内省したり、対策を考えたりすると有効な対処方法へ辿り着きやすくなります。
では、実際にストレス診断を行ってみましょう。以下の12個の設問に答えて、各設問の番号を合計してみてください。
A.あなたの仕事についてうかがいます。
・ひどく疲れた
・気がはりつめている
・ゆううつだ
・よく眠れない
B.最近 1カ月間のあなたの状態についてうかがいます。
・ひどく疲れた
・気がはりつめている
・ゆううつだ
・よく眠れない
C.あなたの周りの方々についてうかがいます。
次の人たちにはどれくらい気軽に話ができますか?
・上司
・同僚
D.あなたが困ったとき、次の人たちはどれくらい頼りになりますか?
・上司
・同僚
合計が19点以上の人は高いストレスを抱えている可能性があります。
今回紹介したストレス診断は厚生労働省のストレスチェックを参考にしています。さらに詳しく知りたい人は下記のリンクからチェックしてみてください。
参考:厚生労働省「5分でできる職場のストレスセルフチェック」
従業員が一定数を超える企業では、企業内でのストレスチェック制度が義務付けられています。こちらもストレスに気付く上では有効ですが、頻度が年に1回と少ないです。そのため、ストレスがかかっていると感じたときにはこまめに自分で確認することが大切です。

次にストレスの原因や影響について考えてみましょう。
以下に当てはまる仕事の人はとくにストレスを抱えやすいと考えられます。
また、一見喜ばしいことに見える「昇進」などもストレスに感じることがあります。
参考:厚生労働省(2020)「労働安全衛生調査(実態調査)」
参考:夏目誠(2008)「出来事のストレス評価」
ストレスを長期間抱えているとさまざまな症状が現れる可能性があります。人によって症状の現れ方は異なりますので、ここでは精神面、身体面、行動面の3点に分けて紹介します。これらの症状は単独で現れる場合もありますが、重複して現れることも少なくありません。
気分の落ち込みやイライラした症状がある、とついストレスが原因と考えがちです。しかし、身体の病気が原因で精神的な症状が現れることもあるため注意が必要です。病気の一例を紹介します。
このような病気が懸念される場合、まずは内科の受診をおすすめします。「心の病気かもしれない」と迷う気持ちがある場合は、精神科もしくは心療内科での受診でもかまいません。診察を踏まえ他科を受診した方がよいと判断された場合には、医師から必要な説明や紹介が行われるからです。

ストレスが高いときの対応方法を3つ紹介します。
コーピングは、英語のcope(=対処する)に由来します。つまり、ストレスへの対処をとり、反応を和らげることを目的としています。
代表的なものとして、「問題焦点型」と「情動焦点型」の2つが挙げられます。
「問題焦点型」は、ストレスの原因を取り除いたり、遠ざけたりしてストレスから抜け出す方法です。
【例】
「情動焦点型」は、ストレスの原因ではなく、ストレスだと思う感情を変化させたり、改めたりしてコントロールする方法です。
【例】
自分でどうしようもない場合、一人で抱え込まず上司に相談することも大切です。すぐに変化が起きるとは限りませんが、今後の業務を調整してもらえたり、配置を見直してもらえたりする可能性があります。
直属の上司に言いづらい場合は、産業医や人事などに伝えることも選択肢の一つです。
症状がひどい場合は病院を受診しましょう。「まだ大丈夫」「そこまでではない」と思って無理をすると悪化しかねません。具体的な受診の目安は以下の通りです。
・症状が2週間以上続いている
・症状が日常生活に支障をきたしている

ストレスがかかる原因や、表出方法は人それぞれです。それらを理解しやすくする方法としてストレス診断を紹介しました。ストレスがかかっている状態を感じたらこまめにチェックすることをおすすめします。そして、自分の状態に合う対処法を考え、悪化を予防してください。