

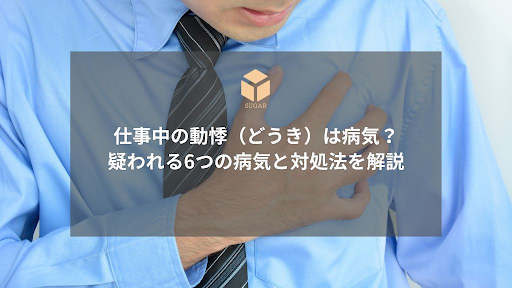
仕事中に緊張して心臓がドキドキした経験を持つ人は多いでしょう。しかし、突然の動悸に襲われたり、時間が経っても落ち着かなかったりすると、次のように心配してしまう人もいるのではないでしょうか。
「なにかの病気ではないのか…」
「どこかおかしいのかもしれない…」
「心臓がドキドキしているのが周囲にばれたくない…」
仕事に支障をきたすほどの動悸は、背景に何らかの病気が隠れている可能性があります。
本記事では、動悸を引き起こす病気について、精神疾患と身体疾患の両面から代表的なものを6つ紹介します。対処法も解説していますので、仕事中に動悸がして不安に感じている人は、ぜひ参考にしてください。
動悸とは、心臓のリズムが一定でないときに起こる身体の違和感を指します。身体の病気以外で動悸が生じる原因として多いのが、急性のストレスです。仕事中に動悸が起こる場合は、以下のようなストレスが影響しているでしょう。
動悸は、ストレスに対抗するための正常な反応だといえます。しかし、頻繁に動悸がしたり、突然心臓の鼓動が速くなったりする場合には、病気が影響しているかもしれません。
動悸の背景に何らかの病気がある場合、原因となる病気を特定して治療を行うことが大切です。動悸を引き起こす精神疾患には、どのようなものがあるのでしょうか。代表的なものとして以下の3つの精神疾患について解説します。
不安障害とは、「悪いことが起きないか心配で何も手につかない」など、不安によって日常生活に支障が出る精神疾患です。動悸は不安障害における典型的な身体症状の1つです。働く上で関連する不安障害としては、「社交不安障害」と「パニック障害」が挙げられます。
「恥をかくのではないか」と人前で注目を浴びることを怖がってしまう精神疾患です。プレゼンや会議での発言、電話対応など、人前で話している姿を見られる場面で動悸が強くなることがあります。
動悸が強くなることで、「緊張していることが周りにばれるのではないか」と余計に心配になってしまうという悪循環が生じやすいでしょう。
パニック障害とは、「死ぬのではないか」と感じるほどの発作的な症状に突然襲われる精神疾患です。激しい動悸に襲われてしまい、発作が起きた場所に行けなくなってしまうケースが多くみられます。
仕事においては、エレベーターや会議中の空間など、閉ざされていてその場を簡単に離れられない状況で生じやすいでしょう。
適応障害とは、ストレスに対抗するための反応が強く出すぎてしまい、生活に支障をきたしている状態を指します。ストレス反応として動悸が強くなる場合があるでしょう。次のような症状がいくつかみられるときには、適応障害が疑われます。
自律神経のバランスが乱れることで、心身に異常が生じる状態が自律神経失調症です。自律神経は、興奮時に活性化する「交感神経」と、リラックス時に強くなる「副交感神経」に分けられます。2つの自律神経がバランスよく働かず、頭痛や胃痛、下痢などさまざまな不調が現れます。
交感神経が優位になると、血流が増大し、動悸が生じやすくなるでしょう。また、緊張した状況から離れても、副交感神経が優位にならず、動悸がおさまらないことも起きやすいといえます。
動悸が起こるのは、ストレスをはじめとした精神的な原因だけではありません。背景に身体の病気が隠れている可能性があります。動悸を引き起こす代表的な身体疾患として、以下の3つを紹介します。
動悸は、心臓の動きに違和感をおぼえる症状であるため、心疾患との関連が強いといえます。動悸がみられる原因として多いのが、不整脈です。一般的な心拍数は50~100回/分ですが、50回以下(徐脈)、100回以上(頻脈)を正常から外れた不整脈とします。
不整脈によって生じる動悸の多くは、期外収縮という自律神経の異常により生じるものです。しかし、一部の期外収縮には、心筋症や狭心症などの疾患が原因になっている場合があり、注意が必要です。
さらに、動悸に加えて突然気を失ってしまうことがある場合、心房細動の可能性があります。脈拍数に注意を払うとともに、動悸に伴ってみられる症状がないかチェックすることが必要でしょう。
気管支喘息では、呼吸がしにくくなるため、心拍数が増加し、動悸を感じる場合があります。頻繁に息苦しくなり、「ゼーゼー」という呼吸音が頻繁にみられる場合は、気管支喘息かもしれません。
気管支喘息は、遺伝的な要因にストレスがかけ合わさって症状が起こるとされています。そのため、これまで症状がみられていなかった場合でも、強いストレスにさらされると発症するケースがあります。また、特定の場面で症状が強く出てしまうこともあるでしょう。
バセドウ病をはじめとする甲状腺機能亢(こう)進症では、心拍数の増加に伴い動悸を感じることがあります。動悸と同時に、身体が熱く汗をかいたり、異常にお腹が減ったりするケースが多いでしょう。
また、更年期障害をはじめとするホルモンバランスの異常によっても動悸が生じることがあります。夜寝ているときに動悸が強くなり、不安や恐怖にさいなまれてしまいやすいでしょう。
仕事中に動悸が生じた場合には、どのように対応すればよいのでしょうか。対処のために必要な3つのステップを解説します。
不安や緊張から動悸が生じ、なかなかおさまらない場合、ストレスが原因だと考えてしまうかもしれません。しかし、背景に身体的な病気が隠れている可能性もあるため、まずは内科を受診して身体に異常がないかを調べましょう。
とくに、徐脈や頻脈がみられたり、動悸が突然始まったりするような症状がある場合は、受診した方がよいといえます。
内科を受診し、身体に異常がなく、ストレスが原因だとわかれば、ストレスから離れるための環境調整を行います。まずは、動悸が起こりやすい場面を振り返り、何がストレスになっているかを特定します。
たとえば、特定の人の言動に影響されて動悸が強くなる場合には、その人とは距離を取るなど、離れるようにします。
ただ、動悸に加えて意欲低下や不眠など精神的な問題があるときには、休職や配置転換などの対処が必要かもしれません。
ストレスが動悸の引き金になっている場合は、メンタル面の治療が必要となります。不安障害や適応障害の診断がつく場合、服薬や心理療法を中心とした治療方法が用いられます。
服薬治療としては、気分を安定させるためにSSRIをはじめとした抗うつ薬の使用が中心です。特定の場面で不安が強く出る場合は、抗不安薬やβ遮断薬で不安や緊張状態を和らげます。
心理療法としては、自律神経のバランスを整える自律訓練法や、動悸の原因になる刺激に徐々に触れていく暴露療法が用いられます。
また、飲酒やカフェインの摂取など、動悸を引き起こす生活習慣を見直し、リラックスできる方法を増やすことも有効です。
いずれも、専門家と一緒に取り組んでいくことで効果が見込まれますので、精神科や心療内科で相談することがおすすめです。
仕事中の動悸は、緊張する場面で起こり、すぐに落ち着く場合は正常な反応だといえます。しかし、突然心臓の鼓動が早くなったり、強い不安感に襲われたりするような場合は、何らかの病気の可能性があります。
また、動悸が生じるのは、精神的な問題だけではありません。心疾患やホルモンバランスの異常など、身体面の異常が隠れていることもあります。
耐えきれないほどの動悸に襲われ、業務上の支障が大きい場合は、内科や精神科を受診することがおすすめです。