

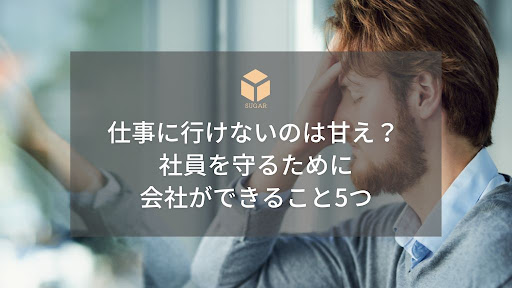
「仕事に行けない」「会社に行くことを考えると苦しい」と感じたことのある人は決して少なくありません。人によっては「単なる甘え」で片づけてしまう人もいます。
「仕事に行かなければ」と頭ではわかっていても、朝になると吐き気や腹痛に襲われたり、不安感や緊張感が強いなど心身に異変が起きて、仕事に行きたくても行けない状態を出勤困難症と言うことがあります。本記事内では、仕事に行けない状態のことを出勤困難症と呼称します。
無理を続けると、うつ病を発症するケースもありますので、心と体のSOSに気づいて早めに対応することが必要です。
本記事では、出勤困難症になる理由と出勤困難症から社員を守る方法について解説します。社員のメンタルヘルス対策に取り組みたいと考えている企業責任者や人事担当者は、ぜひ最後までお読みください。
朝になると仕事に行けない状態は、周りから理解されにくいだけでなく、本人も理由がわからないことがあります。
どうして仕事に行けなくなってしまうのか、さまざまな理由があります。主な理由を3つ解説していきます。
仕事に行けない理由は、人間関係にある場合が多いでしょう。
厚生労働省の調査では、現在の仕事や職業生活に関することで、強い不安やストレスとなっていると感じる 事柄がある労働者(53.3%)について、その内容別労働者割合をみると、「対人関係(セクハラ・パワハラを含む)」が25.7%と上位の理由になっています。
参考:厚生労働省「令和3年 労働安全衛生調査(実態調査)[個人調査](PDF)」
いじめやパワハラ・セクハラをする上司がいる職場では、緊張状態や不安が続いて仕事に行くことがつらくなります。
また、社内で悪口やネガティブな発言が多い、大声で怒鳴る人がいる、イライラしている人が多いという職場は重苦しく、常にストレスにさらされている状態です。
人間関係にストレスを抱えたまま、限度を超えた我慢を続けると、睡眠や食欲など健康に悪影響が出て、出勤困難症になる可能性があります。
毎日のように深夜まで残業、休日出勤も当たり前の時間外労働が常態化している職場では、社員が疲弊してしまいます。
社員同士の協力体制ができていない、情報共有ができていない職場は、仕事の成果も上がらず意欲が下がり、メンタルヘルス不調につながります。
このようなことが続くと、離職率も高くなり、ますます社員が無気力になり、いつのまにか朝起きられない、仕事に行けないということになりかねません。
そもそも仕事が自分に合っていないという場合も、メンタル面に影響を及ぼします。全く興味の持てない仕事や、適性に合っていない仕事をしなければならないことも時にはありますが、それが毎日続くと憂うつになってしまいます。
たとえば、人と話すのが苦手で一人でコツコツ分析する仕事を得意としている人が、外回りの営業をしているような場合です。我慢しながら仕事を続けても結果が出せず、上司から叱られたり正当な評価がされない毎日が続くと、心も体も疲れてしまいます。昇格や出向、海外勤務や勤務先の合併など職場環境の大きな変化が、ストレスの原因になることもあるでしょう。
社員の能力や経験を見極めて、それぞれに適した仕事を任せなければ、社員のモチベーションは下がり、出勤困難症になってしまう可能性があります。
出勤困難症にならないためには、自分自身がストレスに早く気づくことが大事ですが、会社の理解・サポートも欠かせません。職場が原因であれば、同じことを繰り返さないためにも職場の改善が必要です。
事業場におけるメンタルヘルス対策として、心の健康に関する一次予防、二次予防、三次予防があります。
この観点から、会社ができる予防策を5つ解説します。
労働安全衛生法の第三条に、事業者の責任として、「快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」とあります。
ここで言う職場環境は、物理的な環境(温度、湿度、照明、騒音など)、人間工学的な環境(オフィスのレイアウト、作業姿勢など)のみならず、仕事の負荷や自由度・裁量権、人間関係なども含まれます。
業務量や難易度に無理がないか、休日や休暇の十分な取得、適材適所の配置ができているかを見直すことが必要です。昨今は、リモートワークや時短勤務などを取り入れた働き方改革に取り組む会社も増えています。
また、円滑なコミュニケーションがある環境、周りの人に相談しやすい環境であれば、安心して意欲的に仕事に取り組むことができます。
パワハラ、セクハラなどを防止するためのハラスメント研修の実施も欠かせません。
階層別のメンタルヘルス研修を職場に取り入れることは有効です。管理監督者や社員がメンタルヘルス教育・研修を受けることによって、メンタル不調の未然防止や健康増進につながります。
セルフケア、ラインケアのほか、コミュニケーション研修の一環として、傾聴、アサーション、良好な人間関係の構築研修などを実施すると良いでしょう。
また、一次予防に位置づけられているメンタルヘルス対策の一つにストレスチェックがあります。正しいストレスチェックを実施することで、社員自身がメンタルヘルス不調に気づくきっかけとなります。
関連記事:ストレスチェックはなぜ実施する?目的と効果について解説!
| 「傾聴」とは |
| 相手の言うことを否定せず、耳も心も傾けて、相手の話を「聴く」会話の技術を指します。傾聴ができるようになると、異なる価値観を受け入れ、仕事を円滑に進めることにもつながります。経済産業省が提言している「社会人基礎力」に含まれている要素の一つです。 |
| 「アサーション」とは |
| 自分の考え、欲求、気持ちなどを率直に正直にその場の状況にあった適切な方法で相手に伝えることです。職場でのストレスが増加する中、「対等な立場で話せる」「相手に不快感をあたえずにNOを言える」メリットを持つアサーションは、重要なコミュニケーションスキルと考えられています。 |
ラインケアとは、直属の上司などが部下の不調にいち早く気づき、ストレスの軽減に対応することです。
日常的に部下の仕事状況を把握するだけでなく、定期的に面談を行ったり声かけをするなどして、社員が疲労していないか、メンタル不調がないかを把握し、各人の能力や適性に合った配慮が大事です。
異変に気づいたら、できるだけ早く人事部や産業医と連携し、早期に対処をしてください。
ラインケアは、一次~三次予防まで全てを対象としますが、問題の早期発見と早期対処の段階において最もその関わりが重要となるため、当記事では二次予防に分類しました。
日ごろから社内外の保健スタッフ、カウンセラー、産業医との連携体制を作っておくことが大事です。具体的には、相談対応、定期健康診断による早期発見と適切な対応などです。
メンタルヘルス不調に気づいた社員や管理者が相談窓口を活用できるよう周知してください。
また、職場の管理監督者との連携も大事です。少しでも社員の不調に気づいたときに人事部と連携できるようなシステムを構築しておけば、早期対処につながります。
ラインケア同様、保健スタッフや産業医も一次~三次予防まで広く対象としますが、問題の早期発見と対処の段階が、最もその関わりが重要となるため、二次予防に分類しました。
厚生労働省の調査では、過去1年間にメンタルヘルス不調で1カ月以上休業・退職した労働者のいる事業所割合は10.1%となっています。
参考:厚生労働省「令和3年 労働安全衛生調査(実態調査)[事業所調査]」
もちろん、休業する社員が出ないように予防することが大事ですが、休業する社員が復帰するためのサポートも重要です。
休業中の社員に対しては、安心して療養に専念できるように配慮してください。休業中は業務に関する連絡はとらないように心がけ、傷病手当金制度や復職手順などについての情報提供をしてコミュニケーションを欠かさないようにすることが大切です。
主治医や産業医の診断によって職場復帰が可能となれば、復帰支援プランを作成します。元の慣れた職場への復帰が原則ですが、ケースによっては配置転換や異動を検討する必要もあります。
職場復帰後も、上司や主治医などのサポートが欠かせません。定期的なフォローアップの予定を立て、再発防止に努めてください。
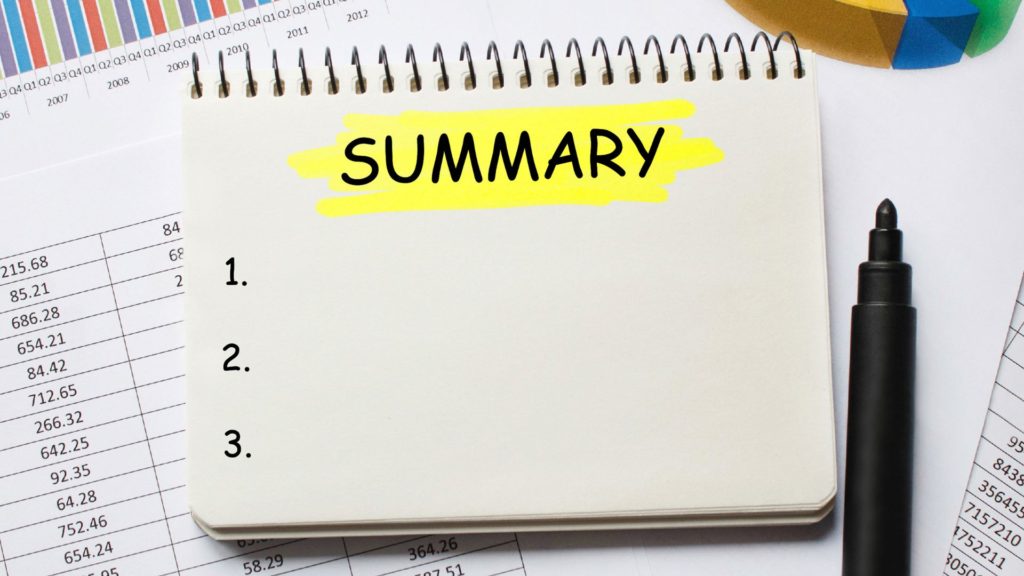
出勤困難症は、体の検査をしても病気の診断がされない場合が多く、体調が悪いと言ってもなかなか周りからの理解が得られません。
本人も「甘え」や「怠けている」からだと自分を追い込んでしまい、我慢し続けてうつ病などを引き起こす場合があります。
何より、周りの理解が必要です。なぜ、仕事に行けなくなるほどストレスを抱え込んでしまったのかを検討して改善に取り組み、休業した社員が安心して戻れるような体制を作ることが大事です。また、普段から、出勤困難症の社員が出ないような予防に努めてください。